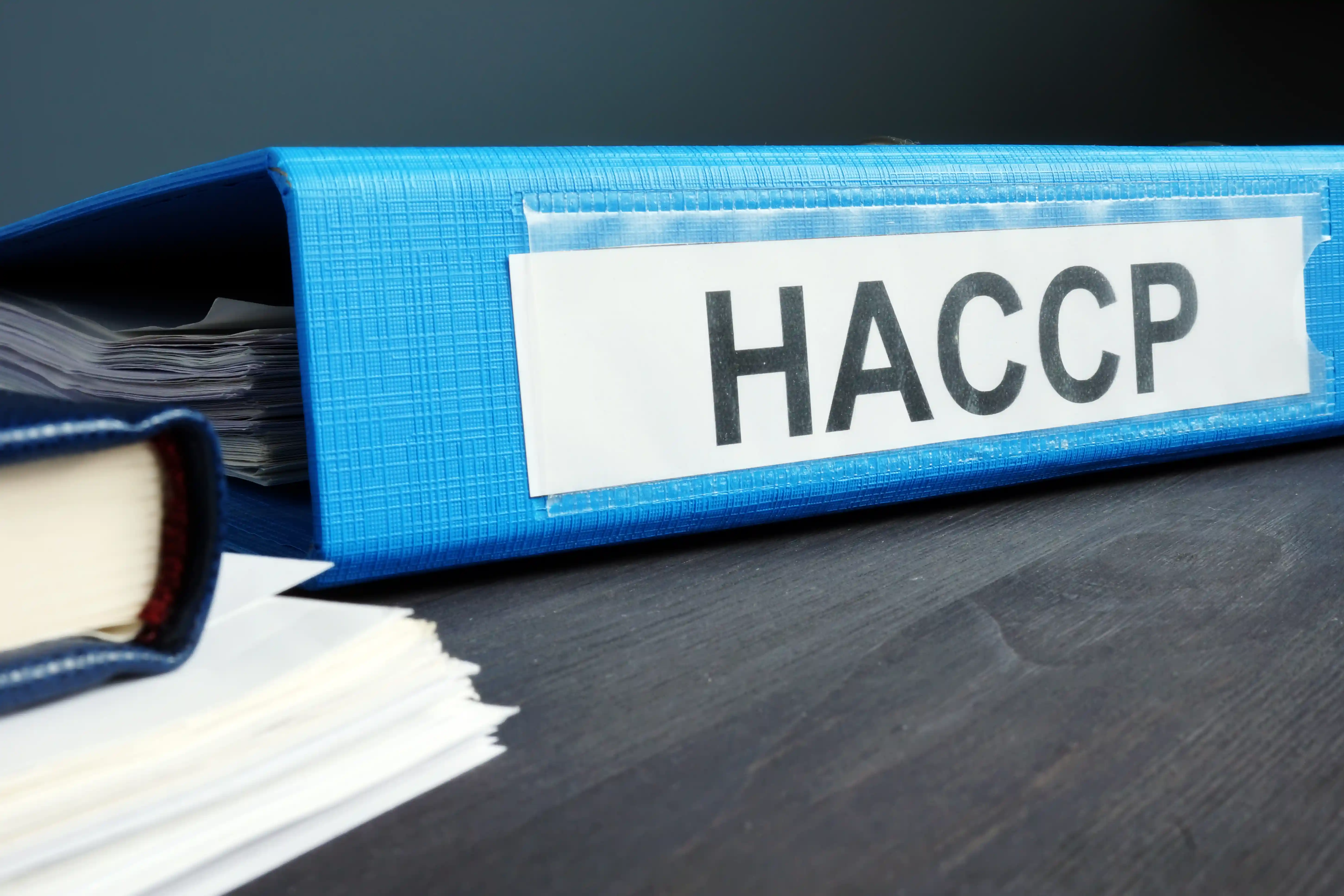- 食品工場の衛生管理の重要性
- 押さえておきたい衛生管理の基本ルール
- 食品工場の衛生管理のマニュアルを作成するポイント
- まとめ
- 衛生管理サポートならお任せください
衛生管理を怠った工場で作られた商品は、食中毒や異物混入などを引き起こす危険性が高まります。食品は人の健康、命に関わる可能性があるため、製造する側は責任をもって安全な商品を製造・販売する必要があります。
そこで本記事では、食品工場における衛生管理の基本ルールから、管理体制の構築方法までを解説します。
食品工場で衛生管理を適切に実施することは、食品事故のリスクを低減につながり、消費者に安全で高品質な食品を提供することができます。その結果、消費者からの信頼に応えることができます。
また、食品衛生法の改正により2020年6月からすべての食品等事業者に対して、HACCPに基づく衛生管理が義務化されました。その後1年間の経過措置を経て、2021年6月からはHACCP導入・運用が完全義務化となりました。
適切な衛生管理体制の構築は、グローバル市場での競争力を高めるためにも重要な要素となっています。
HACCPについて詳しくは、下記の記事をご覧ください。
【関連記事】
HACCPとは何か?基本概念と7原則12手順を解説
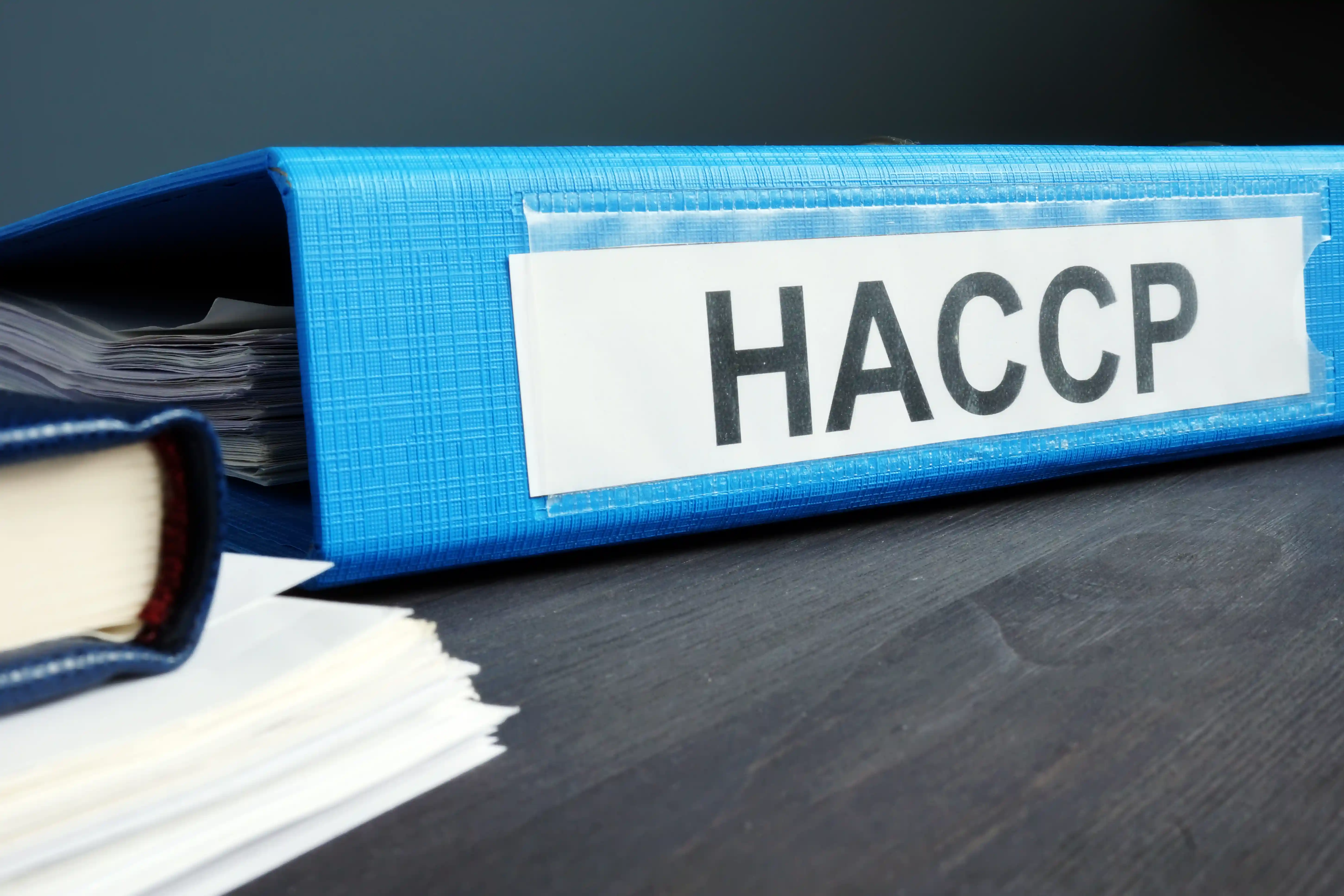
食品工場の衛生管理を徹底するためには、具体的なルールとその実践が欠かせません。 以下で、重要な基本ルールを解説します。
HACCP(HA:危害要因分析、CCP:重要管理点)は、食品製造において安全を確保するための国際的な衛生管理の手法です。危害要因分析(HA)を行い、食品の製造過程で発生する可能性のある危害を特定し、重要管理点(CCP)を設定して管理し、記録付けを行うことで、食品の安全性を高め、消費者へのリスクを最小限に抑えます。
「整理・整頓・清掃・清潔・しつけ」の頭文字を取った5S活動は、衛生管理の基盤を支える重要な要素です。
・整理(Seiri)…不要なものはすぐに捨てる。作業場には必要なものだけ置く。
・整頓(Seiton)…使用器具の置く場所を決め、使った後は元に戻す。必要量以上は置かない。
・清掃(Seisou)…作業後は掃除をする。異物や汚れを残さない。
・清潔(Seiketsu)…時間、手順などのルールを定め、その通りに清掃する。清潔だと判断できる基準を作成する。
・躾(Shitsuke)…従業員が5Sのルールを守り、習慣となるように教育する。現場の状況に合わせてルールを定期的に見直す。ルールをマニュアル化する。
5Sを日常業務に取り入れることで、作業環境を整え、異物混入や汚染リスクを低減できます。
たとえば、清掃スケジュールの徹底や、道具の収納ルールを明確化することで、効率的な作業環境を実現できます。
従業員一人ひとりの衛生意識と習慣が、食品工場全体の衛生レベルに直結します。
従業員には以下を徹底させる必要があります。
・手洗いの徹底…専用の洗浄剤と温水を使用し、適切な手順で洗う。
・作業着の着用…清潔なユニフォーム、帽子、マスク、手袋を着用する。
・健康チェック…出勤時に体調を確認し、下痢や腹痛などの症状がある場合には食品製造に従事させない。
ノロウイルスやサルモネラ属菌等の食中毒につながる可能性のあるウイルスや細菌に感染していると、製造中の食品につけてしまう可能性があるため、定期的に検便を行うことは大切です。症状がでないのに保菌していることもあり、それが原因で食中毒事故を引き起こすことがあります。健康に見えても注意が必要です。
食品に直接触れる機器や器具は、常に清潔を保つ必要があります。作業終了後には、洗浄と消毒を徹底し、使用頻度に応じた点検・メンテナンスを実施します。機械類は可能な限り分解し洗浄を行います。新しい機械を導入する際には、分解洗浄などのメンテナンスのしやすさも選定の基準となります。 また、施設内の壁や床も定期的に清掃し、細菌やカビの発生を防ぎましょう。
異物混入は食品の安全性と品質に大きな影響を与えます。
以下の対策を行いましょう。
・金属探知機やX線検査機の導入…製品中の異物を検出する。
・私物持ち込みの禁止…作業区域に私物を持ち込まないルールを徹底する。
・作業エリアの清掃…製造ライン周辺を常に清潔に保つ。
その他に手袋やラップなど異物となり得る消耗品をブルー等の目立つ色にして、万が一混入しても発見しやすくしたり、清掃時に機械や備品に欠けが無いかチェックしたり、様々な対策があります。
ゾーニングとは、作業区域を清潔区域、準清潔区域、汚染区域に分けることです。ゾーニングにより、交差汚染のリスクを最小限に抑えることができます。
さらに、従業員の動線を制御し、異なる区域間での無駄な移動を防ぐことも重要です。
衛生管理をしていく上で、定期的なモニタリングと検査が必要です。
以下のような取り組みを行いましょう。
・環境モニタリング…ふき取り検査や落下菌検査を行い、作業場の空気や表面の微生物レベルを測定する。
・製品検査…完成品のサンプルを採取し、微生物や異物の有無を検査する。
・記録の保存…検査結果を記録し、問題があれば迅速に改善策を講じる。

衛生管理マニュアルは、従業員が一貫した対応を行うためのガイドラインです。
以下の点を考慮して作成することが大切です。
マニュアルは現場の全従業員が理解できるようにすることが大切です。そのためには、専門用語の多用を避け、わかりやすい言葉で記載しましょう。
また、以下のような工夫を取り入れると、よりわかりやすさが向上します。
・箇条書きや表の活用…手順を簡潔にまとめる。
・イラストや写真の挿入…作業内容を視覚的に理解しやすくする。
・動画形式のマニュアルを採用
・複数言語での表記
各作業について具体的な手順を示し、従業員が迷わずに行動できるようにします。また、すべての手順にはいつ誰が行い、誰が責任者となるのかを明記します。
たとえば、
・手洗い手順…石鹸を使った洗浄からペーパータオルでの拭き取りまで、具体的なステップを記載する。
・清掃スケジュール…毎日の清掃の他、どの機器場所を何日毎に清掃するのか等を細かく明記する。
・検査基準…モニタリングの頻度や合格基準を具体化する。
などを行いましょう。
作業のもれやミスを防ぐため、マニュアルにはチェックリストを添付するのがおすすめです。たとえば、清掃後や作業終了時に記入するチェックリストを用意すると、管理が容易になります。
法規制の変更や現場の状況に応じて、マニュアルを定期的に見直し、更新することが大切です。
・リーダー…現場での衛生管理の実施を確認する。
・従業員 …各自の作業手順を遵守する。
食品工場での衛生管理は、食品の安全性と品質を維持するための基本事項です。適切な衛生管理の実践は、食品製造に関わる企業の責任であり、食品事故のリスクを減らしすべての食品等事業者は、安全な食品を消費者にお届けする必要があります。
また、食品衛生法改正で義務化されたHACCPは国際的な衛生管理手法であり、国内外問わず、商品の安全性を確保する上で取り組む必要があります。
衛生管理を強化するためには、現場での取り組みを徹底し、定期的な見直しと改善を行うことが重要です。最新の衛生管理サービスやツールを活用し、効率的かつ確実な管理体制を構築しましょう。
静岡産業社では自社内に食品衛生検査室を設けており、専門知識を有したスタッフによるHACCP導入のサポートが可能です。
HACCPの導入サポートだけでなく、身近な検査室として微生物検査や衛生調査等も行っております。 是非お気軽にご相談ください。専門的なサポートを通じて、食品安全と事業成長を強力にバックアップいたします。
衛生管理サービスに関してお困りの企業様は、シズサンの衛生管理サービスの詳細ページをご覧ください。