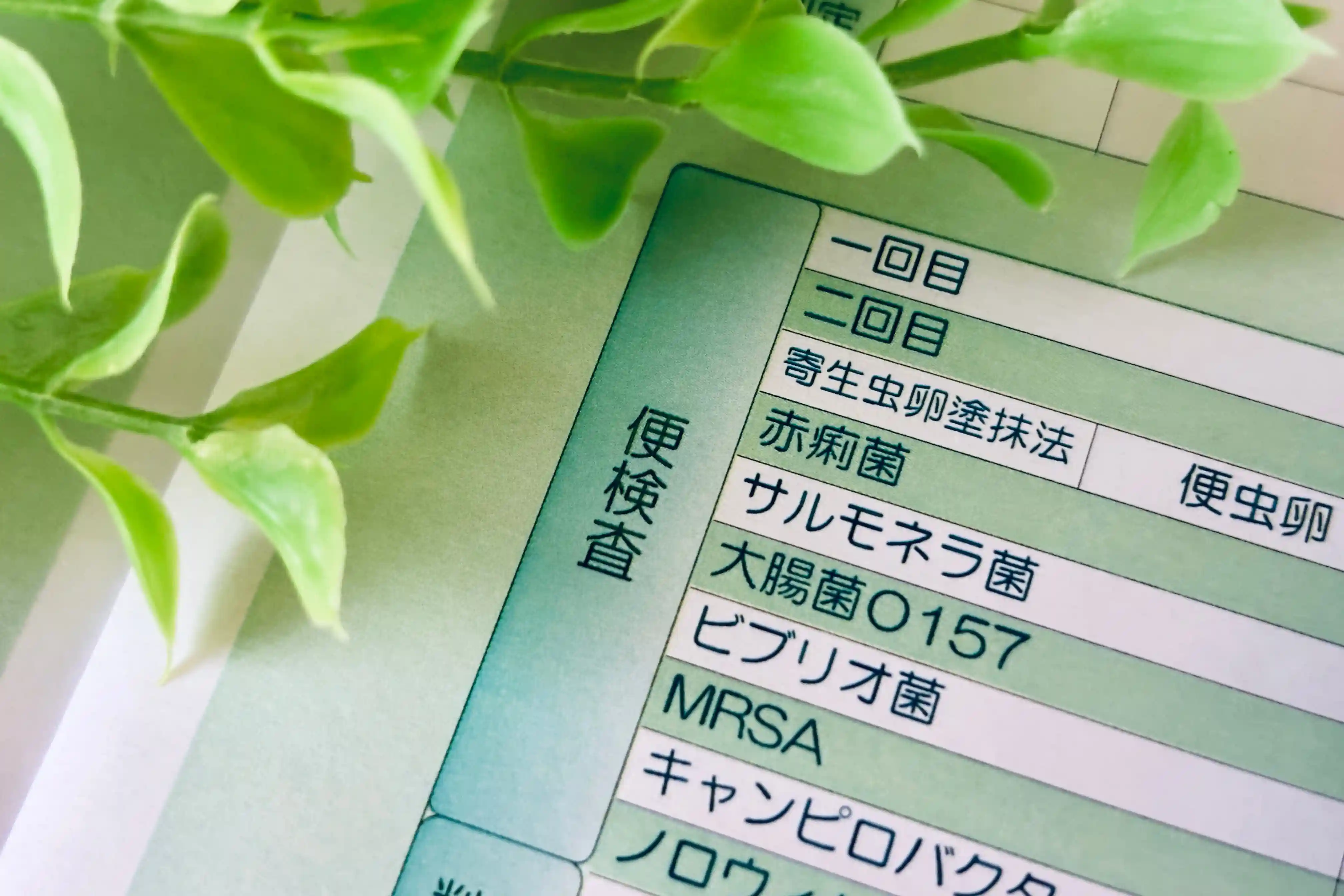食品を扱う事業者にとって、検便の実施は重要な衛生管理の一つといえます。
食品関連企業では従業員の健康状態を確認し、安全性を確保するために検便を行っています。
しかし、「いつ」「どのような頻度」で実施すべきか、その具体的な理由については意外と知られていないことが多いです。
そこでこの記事では、検便が求められる背景や実施のタイミング、そしてその重要性について解説します。
- なぜ検便は必要なのか?
- 腸チフスのメアリー
- 検便と食品衛生法:基本的な理解
- 検便の実施タイミング
- 検便の検査項目
- まとめ
- 衛生検査サポートならお任せください
食品製造に関わる多くの方は、定期的な検便を実施されていることと思います。特に大型調理施設や給食施設では、かなりの頻度で行わなければならず、煩わしいと思われたこともあるのではないでしょうか。では、検便を実施する理由とは何でしょうか?
検便の目的は、健康保菌者(発病はしないが病原体に感染している不顕性感染となり、排菌し感染源となる人)を発見することにあります。しかし、「健康保菌者の発見」と言っても、あまりピンと来ないと思いますので今から100年以上前に、健康保菌者の概念が確立された、ある象徴的な事件をご紹介したいと思います。
メアリー・マローンは世界で初めて臨床報告されたチフス菌(
Salmonella enterica subspecies enterica serovar Typhi)の健康保菌者。彼女はアイルランドからニューヨークに移住したアイルランド系アメリカ人で、今から約100年ほど前となる1900年代初頭にニューヨーク市周辺で発生した腸チフス(Typhoid fever)の感染を自覚せずに広めたことで有名になり、腸チフスのメアリーという不名誉な名称を付けられてしまった女性です。
料理がとても上手なメアリーが使用人として、働くところで腸チフスの感染者が報告されました。保健局はメアリーが感染源であると疑い、メアリーの検便検査を実施したところ、腸チフス陽性と判定されたのです。ところがメアリー自身は、これまで腸チフスを発症したことがありませんでした。つまり保菌者であるという自覚が無いまま人々を感染させる健康保菌者だったのです。
メアリーの便とともに排出されたチフス菌は、手指を経由して料理に付着し、喫食した人々に感染が広がったものと考えられています。
この"Typhoid Mary"「腸チフスのメアリー」のエピソードは、公衆衛生の意識を高めるための教材として、特に食品を扱う人がいかに衛生に対して気を配らなければならないかを学ぶため、恐怖感の与える呼び名とともに今に語り継がれています。

食品衛生法は、食品の安全性を確保するために事業者が従業員の健康状態を管理することを求めています。その一環として、従業員が病原菌を保有していないかを確認する検便が重要な役割を果たします。
検便の目的は、健康保菌者を見つけ、従業員から食品を介して広がる食中毒のリスクを最小限に抑えることです。
メアリーのように本人が知らないうちに病原菌を保有している「健康保菌者」が存在するため、検便によって初めて保菌が明らかになることがあります。
特に、サルモネラや腸管出血性大腸菌、ノロウイルスなどの病原菌やウイルスは少量でも感染リスクが高く、食品業界においては早期発見と対応が重要です。
食品を取り扱う業務に従事するすべての従業員が食品の安全を確保するための重要な役割を担っています。従業員の健康状態を把握し、感染症リスクを低減するために、検便を実施することが求められています。特に、以下のような職種の従業員に対して検便が推奨または義務付けられています。
調理従事者は、食品の加工や調理に直接、携わるため、食品安全の最前線に立つ存在といえます。
調理中に感染源が食品に混入する可能性が高いため、健康状態の管理が必要です。
ホールスタッフや配膳担当者も、間接的に食品に関与するため、検便の対象となります。
料理の提供時や食器の回収時に食品と接触する機会があるなどの理由から、これらの従業員にも検便が求められます。
検便の実施は、これらのリスクを未然に防ぐための重要な手段です。
検便の実施タイミングについては、職種や業務内容によって異なる要件が定められており、定期的な検査を実施することで食品の安全性を確保します。
以下に具体的な職種ごとに検便の実施タイミングを解説します。
食品取扱従事者は、食品の製造、加工、販売、または調理に直接、関与するため、定期的な検便検査が必須とされています。
新たに食品関連業務に従事する従業員に対しては、雇用時に初回の検便を実施し、健康状態を確認します。
大量調理施設衛生管理マニュアル 月1回以上
学校給食衛生管理基準 月2回以上
などのガイドラインが示されています。これらの他に自治体ごとに推奨頻度を示している場合があります。
万が一、食中毒が発生した場合には、保健所の命令等により、関係する従業員全員を対象に緊急検査を実施し、原因究明と感染拡大防止を図ります。
大量調理施設衛生管理マニュアルではノロウイルスなどの感染症が流行する10月から3月には、検査項目にノロウイルスを追加実施することが推奨されています。
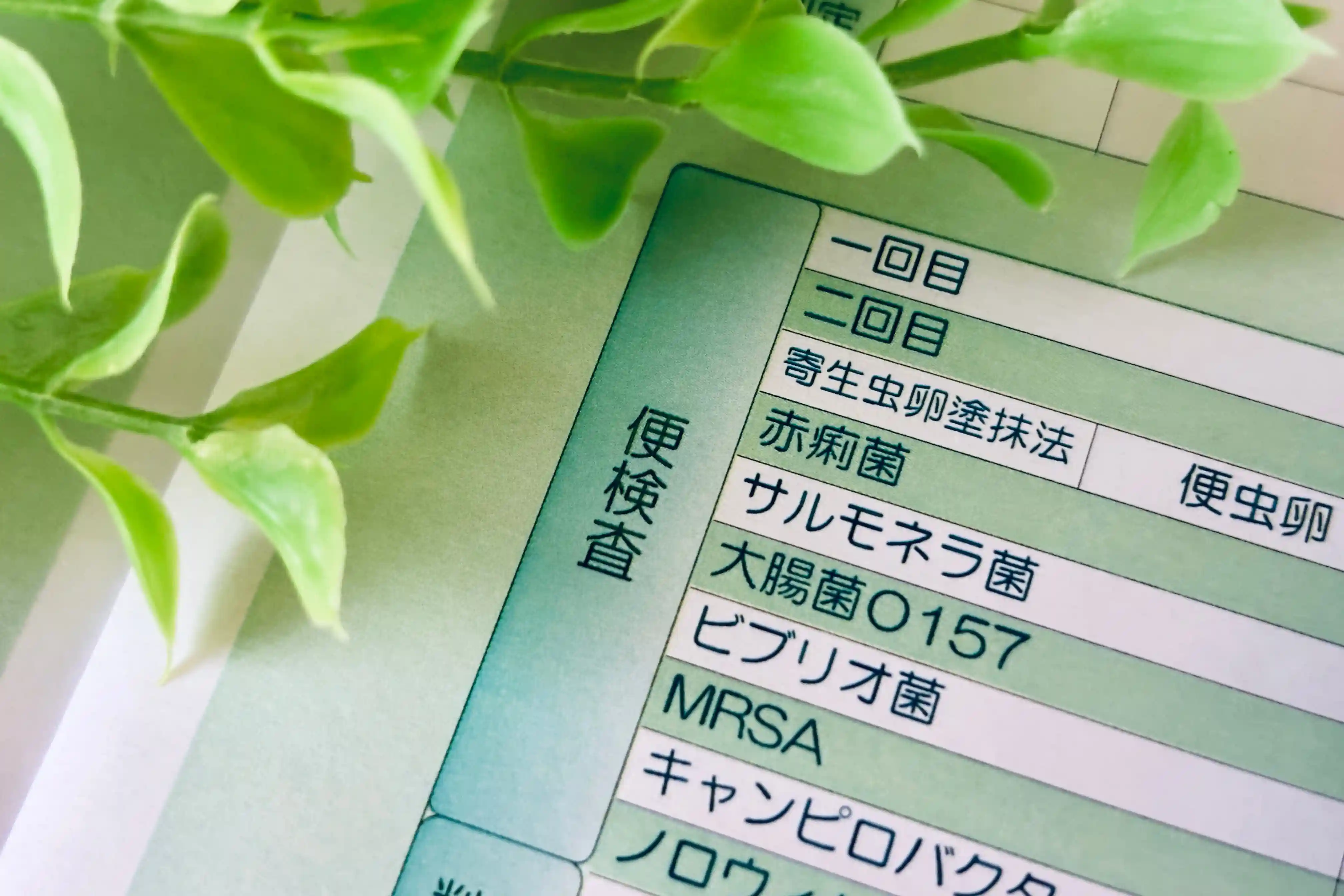
検便は食品従事者の健康状態を確認し、食品の安全性を確保するために行われます。
従業員が保菌していないことを確認するため、特定の病原菌やウイルスを検査します。
以下は、検便で主に実施される検査項目です。
ノロウイルス検査は、特に冬季に重要視される検査項目です。
ノロウイルスは少量でも強い感染力を持ち、集団感染を引き起こすリスクが高いため、早期発見と対応が求められます。ノロウイルスによる食中毒は一年中発生しておりますが、冬季に多く発生する傾向があり、大量調理施設衛生管理マニュアルでは10月から3月においては、ノロウイルスの検査も含めることが望ましいとされています。
腸内細菌検査は、食中毒の原因となる細菌を検出するための基本的な検査です。
この検査では赤痢、サルモネラ(チフス、パラチフスA含む)、腸管出血性大腸菌
が対象となります。
感染症法において第3類に位置づけられる赤痢、腸管出血性大腸菌、腸チフス、パラチフスをセットにして検査を行う事が一般的です。尚、腸管出血性大腸菌には多くの血清型があり、O157が代表的なものですが、このO157だけをターゲットにした検査や、次いで多いO26やO111を加えて検査する場合、すべての腸管出血性大腸菌を検査する場合などがあります。チフス、パラチフスはサルモネラ属の細菌ですので、赤痢、サルモネラ、腸管出血性大腸菌の三項目を検査することがスタンダードです。
また、感染症が流行している地域に渡航された方や来日して間もない方には、コレラや腸炎ビブリオ、他の検査項目の追加をお勧めします。
食品関連事業者にとって、従業員の健康管理は食品の安全性確保に欠かせない要素であり、検便の実施が重要です。検便の目的は、健康保菌者を特定し、食中毒リスクを低減することにあります。過去の「腸チフスのメアリー」事件では、自覚のない健康保菌者が食品を介して病原菌を広めた事例が示されており、公衆衛生管理の重要性が強調されています。
食品衛生法では検便を通じた従業員の健康管理が求められており、特に調理担当者や配膳スタッフなど、食品に直接・間接的に関与する従業員が対象となります。雇用時や定期検査、食中毒発生時、感染症流行時に検便を実施することが推奨されています。
また、検査項目にはノロウイルスや腸内細菌検査が含まれます。特に冬季にはノロウイルス検査が重視され、感染リスクの早期発見と対応が求められます。これらの取り組みを通じて、従業員の健康を守りつつ、食品の安全性を確保することが可能となります。
定期的な検便と適切な管理は、食品関連事業者が顧客の信頼を得る上で重要であり、業界全体の信頼性向上にも寄与します。
静岡産業社では、自社にて衛生検査室を設けており、検便をはじめとする様々な衛生検査サービスを取り扱っております。
検便の実施は、事業者の責務を果たすだけでなく、従業員の健康管理や消費者の安心にも直結します。適切なタイミングで検査を実施し、衛生管理を徹底することで、食品事業者としての信頼を高めることが可能です。
検便の実施を含め、衛生管理の効率化を検討している事業者様は、シズサンの衛生管理サービスをご活用ください。専門的なサポートを通じて、食品安全と事業成長を強力にバックアップいたします。
-
-